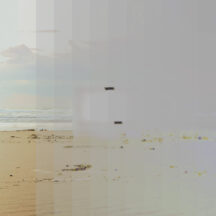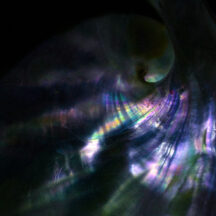「我々は何を写真とするか」という問いへ

本論文では美学者であるモリス・ワイツ(Morris Weitz)とジョージ・ディッキー(George Dickie)の美学理論、ケンダル・ウォルトン(Kendall. L. Walton)の透明性理論とフィクション理論を参照し、写真概念を考察するための問いの転換を試みた。本論文は「写真とは何か」に対する「写真とはしかじかのものである」という答えを導き出すのではなく、「我々は何を写真とするか」という問いに転換し、この問いに対する答えを模索する過程を論じたものである。
本論文の目的は、「写真とは何か」という問いを「我々は何を写真とするか(しているか)」という問いへ転換させ、ものとしての写真だけではなく鑑賞する我々との関係も含めた写真概念を考察することである。今日の写真には社会的な慣習や認知が大きく関わっている。本論文は美学理論やフィクション論などを通した問いの転換によって写真概念を再考した場合、技術的な部分に収束させることなく鑑賞における人々の認識といった部分を含めた写真の定義を求めることができるのではないかという問いのもと、写真概念を構成する諸要素のうち「透明性」と「フィクション」という二つの要素を理論的に整理し検討した。
『写真家の眼』の序論でジョン・シャーカフスキー(John Szarkowski)は《事物それ自体》《細部》《フレーム》《時間》《視点》という5つの項目に分けて写真論を展開している。この論考は「写真がどのように見えるか、そして、なぜ写真がそのように見えるか、についての探究である」とシャーカフスキーが述べているように、写真の特徴として見られる要素を挙げ、「写真とは何か」ではなく「写真がどのように見えるか」について論じられたものである。
シャーカフスキーのように、写真にみられる特徴を抽出しそれぞれについて論じる方法は、多様な側面を持つ写真を理解するために有効であると言える。本論文は主に「透明性」「フィクション」という要素を中心に論じる。どちらの要素もシャーカフスキーが挙げるものではないが、これはシャーカフスキーと私の論じたい「写真」が異なるためである。
シャーカフスキーが論じるのは、「写真がどのように見えるのか」「なぜ写真がそのように見えるのか」という問いのなかにある「ものとしての写真」についてである。一文にするならば、「なぜ写真がそのように見えるのか、その理由は写真にしかじかの特徴がみられるからである」という形式を取ることができるだろう。しかしながら、私の問いを同様の形式にすると、「なぜ写真がそのように見えるのか、その理由は我々が写真(または写真と近い関係にある画像)をしかじかのように扱ってきたからである」となる。ものとしての写真だけではなく、写真を扱う我々との関係から「写真」という概念を考察することで、スクリーンショットや加工が一般化した多様化な写真などを含め、技術の発展とともに今後も変容し続ける写真の様相の一端を捉えることができると考えた。
本論文の第三章において中心的に論じられるウォルトンの「ごっこ遊び(make-believe)」論には社会的な慣例が含まれており、画像を見る経験とそれを取り巻く文脈の関わりを見ることができる。ウォルトンのフィクション論は小説や劇だけでなく絵画や写真といった画像表象にも適用されるものであり、画像とそれを見る我々の関係を考察する方法として妥当であると考えられる。
第一章では、「写真とは何か」という問いから「我々は何を写真とするか」という問いへ変換させ、鑑賞する立場である我々との関係から写真概念を考察することの意義と問題点について論じた。ワイツはこれまでの伝統的な美学理論による芸術概念の定義づけが、「定義できないものを定義しようとしている」ことや、概念の使われ方は開放性を指しながらその概念自体を閉じたものにしようとしているという点で、無益な試みであると批判する。ワイツによれば、芸術概念とその下位概念(小説、絵画、オペラなど)は、事実的にそれが小説や絵画であるか否かではなく、新たに検討されている事例をその概念に含めるために当の概念を拡張することを認めるかについての判断が問題となる。対するディッキーは芸術概念を閉じたもの、下位概念を開かれたものとし、それぞれを「閉じた類/開かれた種」と表現する。ディッキーは下位概念について、個々の芸術作品をそのようなものとして提示するための枠組みであるとして、それぞれの芸術作品には共通する本質的な性質を見ることができると主張する。本章ではワイツとディッキーの論を受け、複数の領域にまたがる作品をある枠組みに置いて提示することが、その作品を当の枠組みの拡張可能性を問う実践として捉えることができるのではないかという可能性を提示した。しかしながら写真分野では、現実と照合させた時の正しさを問われる場面が多々あり、芸術性だけを重視することは困難である。写真概念と密接な関わりをもつ「真正性」について、続く第二章で精査する課題とした。
第二章では、写真に問われる真正性についての考察のために、ウォルトンの透明性理論を検討した。ウォルトンは写真が透明である理由として、スケッチと写真それぞれから情報を取得する時の違いを挙げる。スケッチの場合、そこに描かれたものを信用することは制作者を信用することである。恐竜のスケッチは、それが画家の見間違いであったとしても恐竜のスケッチとして存在することになる。対する写真の場合では、写真家が何を見たかに関わらず、目の前にあったものが写真として写される。写真に写るものは写真家の意図とは無関係に、そこにあるものが決めるのである。これこそ、写真が透明であるといわれる要点である。またウォルトンは、写真を見るという知覚が、鏡や望遠鏡を通して何かを見る時の「見る」と同種のものであるとする。写真の色を変えることができる点などから、鏡などを通して見ることとは異なり、不正確だという反論もあるが、写真が透明であることと現実の正確な写しであるかは別な問題である。ウォルトンは、歪んだ鏡を通して何かを見ることや霧の中でものを見ることを例に挙げ、直接物事を見た場合でも目が欺かれることはあるとして、写真の透明性と真正性がそれぞれ独立したものであると主張する。第二章の最後には、写真が正しいか否かは鑑賞者である我々の判断によるものであるため、写真がもたらす視覚としての機能は写真を見る我々の態度とも密接に関わっていることを論じた。
第三章では、写真を見る時の態度という観点から、写真がもつ画像としてのフィクション性について、ウォルトンのフィクション論を軸に検討した。ウォルトンは、幼少期のごっこ遊びが成人後も表象的芸術作品との関わりの中で続いていると主張する。我々は絵画を見る時、絵具の集まりである平面を見ながら、同時にある人物や風景を見ていると想像する。ウォルトンによれば、絵を見る時の想像活動と知覚経験は密接に結びついている。単純な平面のうちに人物や風景などを見てしまう知覚について、認知説の立場の論者は「目の欺き」とするが、この段階では「心的な事実の確認」であり、絵の内容の理解までは至っていない。この心的事実を「視覚的なごっこ遊び」に属するもの、つまり当の絵画などの画像に見合うような想像に従事することを指定されているものと理解することで、「目の欺き」から一段階進むことができる。
報道写真、芸術写真、記念写真など、写真は社会生活の中で多様な用いられ方をする非常に複雑なメディアである。画像表象としての役割が求められることもあれば、現実に照らし合わせた真正性が求められることもある。写真は置かれる文脈によってその扱いが決まり、我々は当の写真に対し、文脈に沿った役割を求めてきた。今後はより一層増え続けるであろう「写真」概念の拡張を迫る作品実践、特に画像生成AIを用いた作品を中心に写真概念の動向を追うことを今後の課題として位置付けた。